
相続した不動産を売却する流れと注意点相続した不動産を売却する流れと注意点

相続した不動産の売却は、多くの方が人生で初めて経験される手続きです。相続登記から売却、税金の申告まで、通常の不動産売却とは異なる手続きが必要となります。この記事では、相続不動産を売却する際の流れや注意点、税金対策まで、実務経験豊富な不動産会社の視点から詳しく解説いたします
1. 相続不動産売却の基本的な流れ
相続した不動産を売却するには、まず相続登記を完了させる必要があります。相続登記とは、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きのことです。2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料が科される可能性がありますので、早めの対応が重要です。
相続登記が完了して初めて、その不動産を売却する権利が相続人に移ります。つまり、亡くなった方の名義のままでは売却できないということです。相続登記には戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要となり、手続きには通常1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。
2. 相続登記に必要な書類と手続き
相続登記を進めるためには、まず相続人全員を確定する必要があります。そのために被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。これは意外と大変な作業で、転籍を繰り返している場合は複数の市区町村から取り寄せることになります。
相続人が確定したら、不動産をどのように分けるか話し合います。相続人が複数いる場合、全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するのか決定します。たとえば、兄弟3人で親の家を相続した場合、そのうちの1人が不動産を相続して他の2人には代償金を支払うという方法や、不動産を売却して代金を分割するという方法があります。
遺産分割協議がまとまったら、協議書を作成して相続人全員が署名・押印します。この際、実印を使用し印鑑証明書を添付することが必要です。その後、法務局で相続登記の申請を行います。司法書士に依頼するとスムーズですが、費用は10万円前後かかることが一般的です。
3. 相続不動産の売却タイミングと市場調査
相続登記が完了したら、いよいよ売却活動に入ります。ただし、急いで売却する必要がない場合は、市場の動向を見極めることも大切です。不動産市場は時期によって価格が変動しますので、適切なタイミングで売却することで数百万円の差が出ることもあります。
一方で、相続税の納付期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内と決まっています。相続税の支払いに充てるために不動産を売却する場合は、この期限を意識した売却スケジュールを立てる必要があります。納付期限に間に合わない場合、延滞税が発生してしまいますので注意が必要です。
売却を決めたら、まず不動産会社に査定を依頼します。複数の会社に査定を依頼して相場を把握することをお勧めします。査定額は会社によって数百万円の差が出ることもありますが、高い査定額を提示する会社が必ずしも良いとは限りません。査定の根拠をしっかり説明してくれる会社を選ぶことが重要です。
4. 相続不動産売却にかかる税金の種類
相続不動産を売却する際には、複数の税金が関係してきます。まず相続税ですが、これは不動産を含む相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。たとえば相続人が3人の場合、基礎控除額は4800万円となり、相続財産がこれを超えなければ相続税は発生しません。
次に、不動産を売却した際の譲渡所得税があります。これは売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益に対して課税されます。相続した不動産の取得費は、原則として被相続人が取得した時の価格を引き継ぎます。もし購入時の契約書などが残っていない場合は、売却価格の5%を取得費とすることになり、税金が高額になる可能性があります。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。相続の場合、被相続人が取得した日から計算しますので、たとえば親が30年前に購入した家を相続して売却する場合、長期譲渡所得として約20%の税率が適用されます。一方、取得から5年以内の短期譲渡所得の場合は約39%の税率となり、税負担が大きく異なります。

5. 相続不動産売却で利用できる特例制度
相続不動産の売却には、税負担を軽減できる特例制度がいくつか用意されています。最も代表的なのが「相続税の取得費加算の特例」です。これは相続税を支払った場合、その一部を不動産の取得費に加算できる制度で、譲渡所得を圧縮することができます。ただし、相続税の申告期限から3年以内に売却する必要があります。
また「空き家の3000万円特別控除」という制度もあります。これは一定の要件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。たとえば相続した実家が空き家になっており、昭和56年5月31日以前に建築された建物で、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却するなどの要件があります。
この特例を利用できれば、多くの場合で譲渡所得税がゼロになるか大幅に軽減されます。ただし、建物の耐震基準を満たすことや、建物を解体して土地だけを売却するなどの条件がありますので、事前に税理士や不動産会社に相談することをお勧めします。
6. 共有名義の相続不動産を売却する際の注意点
相続人が複数いる場合、不動産を共有名義で相続することがあります。共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要となります。たとえば兄弟3人で3分の1ずつ共有している場合、1人でも売却に反対すれば売却できません。
共有名義のまま時間が経過すると、さらに相続が発生して共有者が増えていき、将来的に売却することが非常に困難になります。そのため、相続が発生した段階で速やかに話し合いを行い、代表者1人の名義にするか、売却して現金化することをお勧めします。
もし共有者間で意見が分かれた場合、自分の持分だけを売却することも法律上は可能ですが、実際には買い手を見つけることは非常に困難です。持分だけを購入しても単独で利用や処分ができないため、市場価格よりもかなり安い価格でしか売却できないのが現実です。
7. 相続不動産の売却価格の決め方
相続不動産の売却価格は、相続税評価額とは別に市場価格で決定されます。相続税の計算に使用される路線価は、実際の市場価格の約80%程度に設定されていることが一般的です。そのため、相続税評価額が3000万円の不動産でも、実際には3500万円から4000万円程度で売却できる可能性があります。
売却価格を決める際は、周辺の取引事例や現在の市場動向を参考にします。また、建物の状態や立地条件、接道状況なども価格に大きく影響します。たとえば角地で日当たりが良く、駅から近い物件は高く評価されますが、間口が狭く奥行きが長い旗竿地などは評価が下がります。
価格設定は売却期間にも影響します。相場よりも高めに設定すると売却までに時間がかかり、低めに設定すると早く売れますが利益が減ります。相続税の納付期限がある場合は、余裕を持った価格設定と売却スケジュールを組むことが重要です。
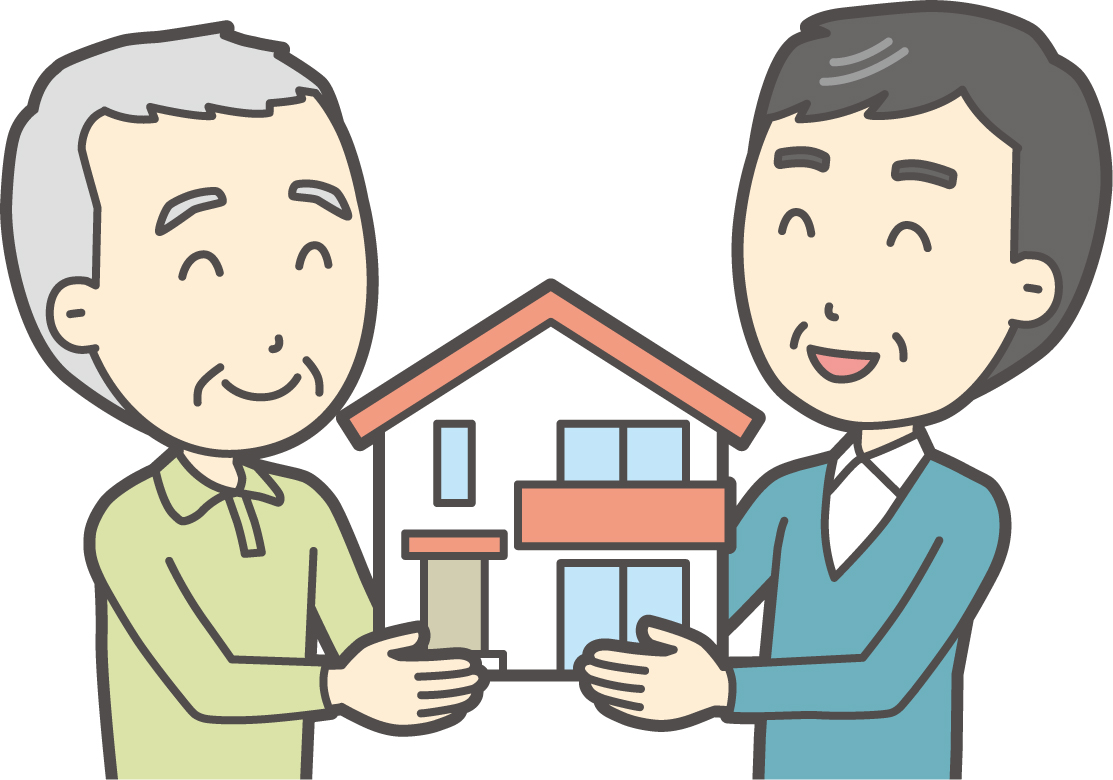
8. 相続不動産の現状を確認するポイント
相続した不動産を売却する前に、物件の現状をしっかり確認することが大切です。長年空き家になっていた場合、建物の老朽化が進んでいる可能性があります。雨漏りやシロアリ被害、設備の故障などがあれば、売却前に修繕するか、現状のまま価格を下げて売却するか判断する必要があります。
また、境界が確定しているかも重要なポイントです。隣地との境界が曖昧な場合、測量を行って境界を確定させてから売却することをお勧めします。境界が不明確なまま売却すると、後々トラブルになる可能性があり、買主が見つかりにくくなります。測量費用は50万円から100万円程度かかりますが、スムーズな売却のためには必要な投資です。
さらに、物件に抵当権などの権利が設定されていないか確認します。被相続人が住宅ローンを組んでいた場合、抵当権が登記されている可能性があります。ローンが完済されていれば抵当権を抹消できますが、残債がある場合は売却代金で返済するか、別途資金を用意する必要があります。
9.相続不動産売却時の必要書類
相続不動産を売却する際には、通常の不動産売却よりも多くの書類が必要になります。まず相続登記が完了していることを証明するために、登記簿謄本(登記事項証明書)が必要です。これは法務局で取得できます。
次に、固定資産税の納税通知書や評価証明書も必要です。これらは毎年4月から6月頃に市区町村から送られてきます。もし手元にない場合は、市区町村の税務課で再発行を依頼できます。売却時には固定資産税の精算を行いますので、最新年度のものを用意しておきましょう。
建物の図面や設備の説明書なども、あれば買主への説明に役立ちます。特に新しい建物の場合、確認済証や検査済証があると買主の安心材料になります。また、リフォームや修繕の履歴がわかる書類があれば、物件の価値を適切に評価してもらえます。
10.相続不動産売却の媒介契約の選び方
不動産会社に売却を依頼する際は、媒介契約を結びます。媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。それぞれにメリットとデメリットがありますので、状況に応じて選択することが大切です。
専属専任媒介契約は、1社だけに売却を依頼する契約で、最も拘束力が強い契約です。不動産会社は1週間に1回以上の報告義務があり、積極的に販売活動を行ってくれます。ただし、他社に依頼できないため、その会社の販売力に売却が左右されます。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。競争原理が働いて早く売れる可能性がある一方で、各社の販売意欲が下がる傾向があります。人気エリアの物件や、すぐに売れそうな好条件の物件には向いていますが、売却に時間がかかりそうな物件の場合は専任系の契約の方が良い結果が出やすいです。
11.相続不動産売却後の確定申告
不動産を売却して利益が出た場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。会社員の方で普段は確定申告をしていない場合でも、不動産売却の年は申告が必要になりますので注意してください。
確定申告では、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得を計算します。取得費には被相続人が購入した時の価格のほか、購入時の仲介手数料や登記費用なども含まれます。譲渡費用には売却時の仲介手数料、測量費用、建物の解体費用などが該当します。
特例を利用する場合は、申告書に特例適用を記載し、必要な添付書類を提出します。たとえば空き家の3000万円特別控除を利用する場合は、被相続人居住用家屋等確認書という書類を市区町村から取得して添付する必要があります。手続きが複雑ですので、税理士に相談することをお勧めします。
12.まとめ
相続した不動産の売却は、相続登記から始まり、市場調査、売却活動、税金の申告まで、多くの手続きが必要です。特に税金面では、適切な特例を利用することで大きな節税効果が期待できますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
また、相続人が複数いる場合は、早めに話し合いを行い、全員が納得できる形で手続きを進めることが大切です。時間が経過するほど関係者が増えたり、意見がまとまりにくくなったりする傾向がありますので、相続が発生したら速やかに対応しましょう。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。競争原理が働いて早く売れる可能性がある一方で、各社の販売意欲が下がる傾向があります。人気エリアの物件や、すぐに売れそうな好条件の物件には向いていますが、売却に時間がかかりそうな物件の場合は専任系の契約の方が良い結果が出やすいです。
センチュリー21クレール不動産では、相続不動産の売却について豊富な経験とノウハウを持つスタッフが、お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。相続登記のサポートから売却活動、税理士のご紹介まで、ワンストップでお手伝いさせていただきます。相続不動産の売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
(注)本コラムは2025-10-20時点の情報に基づき作成しています。制度や相場は変動するため、最新の情報が必要な場合はご連絡ください。



























